不動産を売却する際には税金を納める必要があります。
税額をできるだけ抑えたい、というあなたにこそ知ってほしい不動産売却の税金対策をまとめました。
この記事を読んで、税金に悩むことなくスマートな不動産売却を行いましょう!
「まずは不動産売却の基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。
不動産売却に課される税金とは
よし、税金対策をしよう!と意気込む前に、まずは不動産売却時にどんな税金がいつかかるのかを把握しておきましょう。
最初に、不動産売却に関係する税金の種類とタイミング、金額の目安を以下の表で確認しましょう。
| 税金 | 内容 | 納税タイミング | 税金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 印紙税 | 契約書などの課税文書の作成に対してかかる | 売買契約書作成時 | 契約金額によって値段が異なり、 1,000円~30,000円の間に収まることが多い。 |
| 譲渡所得税 | 売却で得た利益に対してかかる | 売却した翌年の確定申告時期 | 利益額によって大きく変わり、 数十万~数百万かかるケースも。 |
| 登録免許税 | 登記を設定した時に課される | 不動産の決済・引き渡しの日 | 不動産1つあたり1,000円。 |
印紙税とは
印紙税は、契約書や領収書など特定の文書に貼付される印紙に課せられる税金です。
この税金は、契約の成立や取引の証明として重要な文書に対して課され、取引される金額に応じて印紙の金額が異なります。税率は一定の基準に基づいて設定されており、文書によっては数百円から数万円に及ぶこともあります。取引の規模が大きいほど高額な印紙が必要になるということです。
印紙税は、売買契約を正式に結ぶ際に必要になります。契約書に印紙を貼り、契約当事者が署名・捺印をすることで、契約が法的に有効となり、同時に印紙税が支払われることになります。
これは契約書の正式性を保証するための重要な手続きの一部です。不動産取引の場合、通常は売主が印紙税を負担することが多いですが、これは取引の条件によって異なる場合もあります。
不動産売却でかかる印紙税についての詳細は、こちらの記事でまとめてあります。ぜひご覧ください。
譲渡所得とは
一方、譲渡所得税は所有する不動産を売却して得た「利益」である譲渡所得にかかる税金であり、場合によって大きく金額が変動します。
譲渡所得税が必要になるタイミングは、不動産を売却して利益が出た後、その年の確定申告時です。売却した翌年の確定申告期間に申告・納税する必要があります。
譲渡所得税の計算方法
さて、税金対策に利用できる税金が譲渡所得税であることがわかったところで、実際にその譲渡所得の計算方法を確認しましょう。
ここで注意したいのは、譲渡所得は売却金額そのものではなく、売却金額から必要経費を差し引いた金額であるということです。
必要経費とは、その不動産を買ったときの代金とかかった費用である取得費、および売却にかかった費用である譲渡費用です。
譲渡所得=売却金額ー(取得費 + 譲渡費用 )ー特別控除額
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
上記のように譲渡所得税は譲渡所得に応じてかかるため、譲渡所得が少なければ少ないほど、譲渡所得税の額が少なくなります。この計算がマイナスになる場合には税金はかかりません。
また、不動産売却時の譲渡所得税の税率は、譲渡所得の額や所有期間によって異なります。
短期(5年未満)保有の場合は、税率「39.62%」
で税率が異なり、また所得の額によっても税率が変わります。税金対策では、この税率と譲渡所得をどこまで少なくすることができるかがカギとなります。
また、譲渡所得を計算するためには、売却によるお金の出入りを正確に整理・記録しておき、どの費用を加えてどの費用を差し引くのか正しく知っておく必要があります。
なお、古くからの持ち家などで取得費がわからない場合は、取得費を売却金額の5%として計算してもよいこととなっています。
登録免許税とは
登録免許税とは、日本において不動産の所有権移転や抵当権設定などの登記に際して必要となる税金です。この税金は、不動産取引に伴う法的な手続きの一環として発生します。
不動産売却時の登録免許税の相場は、対象となる不動産の種類や価値によって異なります。一般的には、不動産の評価額の一定割合が登録免許税として計算されます。
この税金が必要になるタイミングは、所有権移転登記を行う際です。不動産を売却した後、新しい所有者の名義に登記を変更する際に登録免許税が発生します。この手続きは売買が成立した後に行われるため、通常は売買契約の完了後に必要となります。
以上のことから、この中で税金対策に利用できる税金は譲渡所得税のみです。
かかる費用・税金は不動産の種類や状況によって異なります。そこで、かかる費用・税金を簡単にチェックしましょう!
必要項目を選択して「かかる費用・税金を見る」を押すと、ご自身の場合にかかる金額や項目の内訳が一覧で表示されます。
 不動産の種類
不動産の種類| 費用・税金名 | 金額 | 内容 |
|---|
| 控除名 | 内容 |
|---|
不動産売却の税金対策の方法
不動産売却における税金対策は、売却によって得られる利益を最大化し、税負担を最小限に抑えるための重要なステップです。
この章では、効果的な税金対策の方法を探求し、不動産売却時に適用可能な様々な税制優遇措置や節税テクニックを紹介します。具体的には、所有期間が5年超えてから売却する取得費をできるだけ多く計上する、譲渡費用をできるだけ多く計上するなど、多角的なアプローチを通じて、不動産売却に伴う税金の負担を軽減する方法を詳しく解説します。これらの情報は、不動産を売却する際の重要な参考情報となるでしょう。
まずこの章では、不動産を売却する方、ほぼ全員に適用可能な税金対策について紹介していきます。
所有期間が5年を超えてから売る
前章の最後に少し触れたように、税率は売却する不動産の所有期間によって大きく異なります。
不動産の所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年越えなら長期譲渡所得となります。
- 短期譲渡所得:売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合適用。税率は39.63%
- 長期譲渡所得:売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合適用。税率は20.315%
これは転売目的による短期の不動産売買を抑えるために設けられた区分です。
長期譲渡所得の税率の方が税額を抑えられるため、所有期間が5年を超えてから不動産を売却することが税金対策に繋がります。
なお、所有期間は不動産を取得した日から売却した日までの期間を指します。
取得した日とは、原則として不動産の引き渡しを受けた日です。
また、売却した日とは、原則として売主が買主に不動産を引き渡した日です。ただし、その年の1月1日時点で判定されるので、注意が必要です。
いずれの場合も売買契約日を選ぶこともできるので、覚えておきましょう。
取得費をできるだけ多く計上する
譲渡所得を減らすため、取得費をもれなく計上することは税金対策にとって非常に重要です。
取得費とはその不動産の取得にかかった費用を指します。以下の表は、取得費として計上可能なものです。
- 購入代金や建築代金(建物は減価償却費相当額を差し引く)
- 取得時に支払った仲介手数料
- 契約書の印紙税
- 登記費用(登録免許税、司法書士への報酬など)
- 不動産取得税
- 購入時に支払った立ち退き料(借主がいた場合)
- リフォーム費用
- 測量費(土地の場合)
- 土地の造成費用(土地の場合) など
これらをもれなく計上しましょう。
譲渡費用をできるだけ多く計上する
税金対策として、取得費同様に譲渡費用ももれなく計上しましょう。
譲渡費用とは、その不動産を譲渡する際にかかった費用を指します。以下の表は、譲渡費用に含まれるものです。
- 売却時に支払った仲介手数料
- 契約書の印紙税
- 売却時に支払った立ち退き料(借主がいた場合)
- 建物の解体費用
- 測量費(土地の場合) など
【ケース別】不動産売却の税金対策方法
ここからは、売却予定の不動産に適用できる税金対策をケースごとに解説します。方法が適応できるケースとできないケースがありますので、ご自身の不動産ではどの税金対策が適用できるかしっかりご確認の上利用してください。
特に、マイホーム(居住用不動産)を売却する場合、売却代金は買い替えやその後の生活などで必要な資金でもあることから、有利な特例が用意されています。
それらの特例を使えるかどうかで税金は大きく変わります。条件などを詳しくチェックしていきましょう。
マイホームの売却:3,000万円が控除される
マイホームの売却なら譲渡所得から3,000万円を差し引ける特例があります。それが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」です。
この控除はその不動産の所有期間を問われることがないため、非常に利用しやすい特例です。譲渡所得が3,000万円までなら税金がかからないことになります。
控除は一人につき最大3,000万円です。そのため、建物や土地が夫婦の共有名義なら、合計6,000万円までの控除が可能になります。
主な適用条件は、自分の住む建物・土地の売却であること、売却した年の前年/前々年にこの特例や居住用財産の買い換え特例などの適用を受けていないこと、配偶者や親族・自分がオーナーである会社への売却ではないことです。
詳しくは国税庁タックスアンサーNo.3302「マイホームを売ったときの特例」をご覧ください。
所有期間10年超えマイホームの売却:軽減税率が適用される
マイホームの所有期間が10年を超えている場合、軽減税率を適用できます。それが「所有期間10年超の軽減税率」です。
譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について、通常20%の長期譲渡所得の税率が、14%になります。これは3,000万円特別控除と併せて利用できるので、覚えておきましょう。
詳しくは国税庁タックスアンサーNo.3305「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」をご覧ください。
マイホームを売って買い換える:税金の繰り延べができる
マイホームを売って新しいマイホームに買い換える場合、一定条件を満たせば譲渡所得に対する税金を繰り延べできます。これを「居住用財産の買い換え特例」といいます。
これは、税制優遇措置で、買い換え時の税金を軽減できます。
条件は、売却するマイホームの所有期間が10年を超えていることです。
注意したいのは、この特例によって税金が免除されるわけではなく、先送りされるということ。
次に買い換えした場合に、繰り延べ分を含めて課税されることになります。
売るマイホームが新しいマイホームより高いか同額なら、税金は全額繰り延べになります。新しいマイホームの方が安い場合は、その差額に税金がかかります。
ここで注意したいのが、「居住用財産の買い換え特例」と「3,000万円特別控除」(および「所有期間10年超の軽減税率」)は併用ができないということです。
どちらも使える、となった場合には、試算により有利な方を選びましょう。
詳しくは国税庁タックスアンサーNo.3355「特定のマイホームを買い換えたときの特例」をご覧ください。
事業用不動産売却:税金の繰り延べができる
マイホーム以外で、個人が店舗・事務所・農地・賃家・貸地などの事業用不動産を売って、新しい事業用不動産を買い換えた場合にも買い換え特例を受けることができます。これを「事業用資産の買い換え特例」といいます。一定条件を満たせば、売却金額の80%を繰り延べすることもできます。
適用条件が多いので、事前に確認をしておきましょう。
- 売却・購入ともに事業用の不動産であること
- 売却・購入する不動産が一定の組み合わせであること
- 土地の場合、購入する土地が売却する土地面積の5倍以内であること
- 売却した年、またはその前年/翌年中に購入すること
- 買い換えから一年以内に、その不動産で事業を行うこと
なお、店舗併用住宅の場合は、居住用部分は居住用財産の買い換え特例が、店舗部分は事業用資産の買い換え特例が使える場合もあります。
詳しくは国税庁タックスアンサーNo.3405「事業用の資産を買い換えたときの特例」をご覧ください。
相続した空き家の売却:3,000万円が控除される
空き家となった親などの家の相続・売却でも、条件により3,000万円の控除を受けることができます。これを「空き家の3,000万円特別控除」といいます。
被相続人が亡くなった時にその家に住んでおらず、老人ホームなどに入所していた場合も適用対象です。
適用条件として、売却を相続開始から3年目の12月までに行うことと、建物が一定の耐震基準を満たしている必要があります。そのため、耐震改修を行ってから売却するか、建物を解体して更地にしてから売却する必要があります。
一定条件を満たせば小規模宅地等の特例や3,000万円特別控除、居住用財産の買い替え特例と併用も可能です。
ただし、この特例は令和5年12月31日まで適用可能であるため、注意が必要です。
詳しくは国税庁タックスアンサーNo.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」をご覧ください。
相続税を納めている不動産の売却:取得費に加算できる
相続した不動産について相続税を納めていれば、相続税の一部を「取得費」に加えることができます。これを「相続税の取得費加算の特例」といいます。
取得費は必要経費として、売却金額から差し引くことができるため、そのぶん節税が可能です。
相続開始の翌日から3年以内の売却であることなどが条件で、売却の翌年に確定申告が必要です。
詳しくは国税庁タックスアンサーNo.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」をご覧ください。
平成21年・22年に購入した土地の売却:1,000万円が控除される
国税庁のホームページにもあるように、平成21年1月から平成22年12月の間に購入した土地(借地権も含む)は、売却の際に譲渡所得から最大1,000万円を差し引くことができます。マイホーム以外の土地でも可能です。
ただし、3,000万円特別控除など、ほかの譲渡所得の特例との併用はできません。
また、相続や贈与、配偶者や一定の親族など特別な関係にある相手からの購入は対象外となります。
詳しくは国税庁タックスアンサーNo.3225「平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」をご覧ください。
ふるさと納税をした場合:寄付金控除の対象となる
自分の所属している自治体以外の自治体に寄付をし、返礼品をもらえる「ふるさと納税」。
もし「ふるさと納税」に寄付をしている場合、寄付合計額から2,000円(自己負担金)を除いた額が、寄付金控除の対象となります。
つまり、住民税から控除、所得税から還付されることになります。
なお、「ふるさと納税」で節税する場合は控除上限額の試算も必要です。上限額は年収に応じて決まるので、予測を立てて計算をしましょう。
詳しくは国税庁タックスアンサーNo.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」をご覧ください。
相続物件の税金控除特例
相続物件の税金控除特例は、相続によって不動産を取得した際に適用される税制優遇措置です。この特例を利用すると、相続物件を売却した際に生じる譲渡所得に対する税負担が軽減されます。
特例を適用するためには、いくつかの条件を満たす必要があり、以下が例の一部です。
- 相続の事実:特例を適用するためには、不動産が相続によって取得されたことが必要です。
- 所有期間:相続から売却までの期間が特定の年数以上である必要があります。この期間は、相続開始日から譲渡日までを指します。
- 物件の種類や利用状況:特例が適用されるのは、居住用不動産や特定の条件を満たす土地など、特定の種類の物件に限られる場合があります。
- 譲渡所得の金額:譲渡所得の金額によって、控除額や適用条件が異なることがあります。
農地の税金控除特例
農地の税金控除特例とは、農地の売却に伴い発生する譲渡所得に対して適用される税制上の優遇措置です。この特例は、農業用地を他の目的に転用する際に、税負担を軽減することを目的としています。
税金控除特例を受けるための条件は以下の通りです。
- 農地の種類:特定の条件を満たす農地であることが必要です。
- 所有期間:農地を一定期間以上所有している必要があります。
- 転用計画:農地を非農業用途に転用する計画があることが条件となる場合があります。
- その他の要件:地域や農地の種類に応じて、追加の要件が設定されることがあります。
農地の売却に際しては、これらの条件を満たすことで税負担を軽減できる可能性がありますが、具体的な条件は変更されることもあるため、最新の情報を確認することが重要です。
事業用不動産の税金繰り延べ
事業用不動産の税金繰り延べとは、事業用の不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対する税金の支払いを、一定の条件下で後ほどに延期する制度です。これにより、資金の流動性を高め、新たな事業投資に向けた柔軟な資金計画が可能になります。
税金繰り延べの特例を受けるための条件には、以下のようなものが含まれます。
- 対象となる不動産
事業用として使用されている不動産であることが必要です。 - 再投資の計画
売却した資金を新たな事業用不動産への再投資に利用する計画があること。 - 再投資の期間
再投資は売却から特定の期間内に行われる必要があります。 - その他の要件
法律によって規定されるその他の要件を満たす必要があります。
これらの条件を満たすことで、事業用不動産の売却による税負担を効果的に管理し、事業展開のための資金をより柔軟に運用することが可能となります。
【損失が出た場合】不動産売却の救済措置
譲渡損失が出た場合の特例とは、不動産などの資産を売却して損失が発生した際に適用される税制上の措置です。
マイホームを売って赤字になることもあります。それは、購入した金額より売却した金額の方が少ない、譲渡損失が発生したが、売却した金額では残っている住宅ローンを完済できない、損は出たが新たに住宅ローンを組んで新しいマイホームを購入したい、という状況の際に使います。
この特例では、売却による損失(譲渡損失)を他の所得と相殺することができる「損益通算」や、その損失を翌年度以降に繰り越して所得から控除する「繰越控除」が可能です。
この章知っておきたい救済措置について解説します。損失を上手に活用して、節税を目指しましょう。
譲渡損失の損益通算
譲渡損失が出た際、給与所得などの他の所得から譲渡損失を差し引くことができます。これを「損益通算」といいます。
これにより、課税所得が少なくなり、その年の税金が軽減されます。
この特例は不動産の買い換えを行う場合にも利用できます。
なお、住宅ローンが残っている場合、譲渡損失の上限は、売却時の住宅ローン残高から売却金額を引いた額です。
詳しくは国税庁タックスアンサーNo.3370「マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき」をご覧ください。
譲渡損失の繰越控除
損益通算に加え、その年の所得から引ききれなかった損失金額があれば、翌年以降に繰り越して、その年の所得から差し引くこともできます。これを、「繰越控除」といいます。
損失金額は3年間繰り越しが可能です。
特例の適用には、売却の翌年に確定申告が必要となります。
詳しくは国税庁タックスアンサーNo.3203「不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合」をご覧ください。
不動産を売却した結果、手元に残るお金を多くする一番良い方法は、そもそも不動産を高値で売却することです。
そして、不動産の売却は、多くの場合そのほとんどを不動産会社に任せてしまうので、不動産売却が成功するかどうかは良い不動産会社を選べるかどうかにかかっています。
不動産の査定価格は、プロである不動産会社でも会社によって大きく異なることが少なくないからです。複数の不動産会社に査定を依頼するのであれば、一括査定サービスを活用するのが便利でしょう。
数ある一括査定サービスの中でも、提携不動産会社数が1,700社もあるイエウールがおすすめです。提携不動産会社数が多いことで郊外でも豊富な不動産会社の紹介を受けられます。これから売却する予定の方は、完全無料で利用できるのでぜひ一度試してみてはいかがでしょうか?
あなたの不動産、
売ったらいくら?
あなたの不動産、
売ったらいくら?



 住宅ローン
住宅ローン 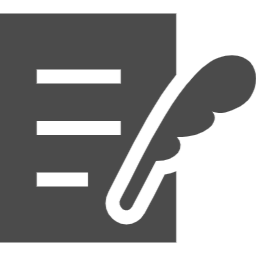 抵当権の抹消
抵当権の抹消  保有期間
保有期間 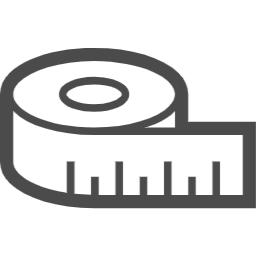 測量を行うか
測量を行うか 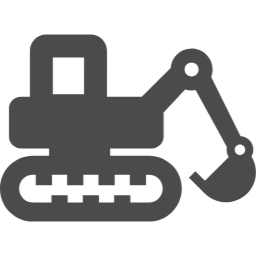 解体してから売るか
解体してから売るか 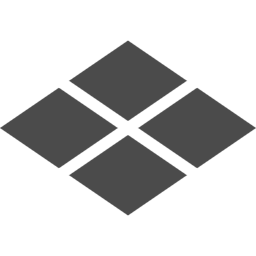 坪数
坪数  ごみ処分するか
ごみ処分するか  ハウスクリーニングするか
ハウスクリーニングするか 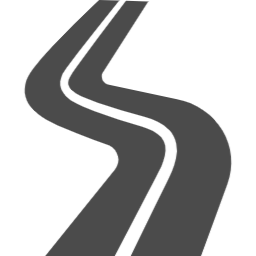 物件の入手経路
物件の入手経路 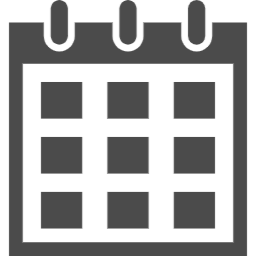 建築年月
建築年月 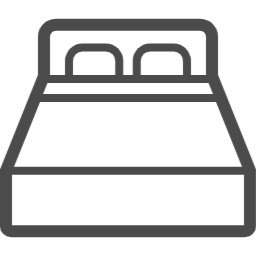 住んでいた時期
住んでいた時期