「まずは不動産売却の基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。
不動産売却にかかる税金はいつ払う?
結論からお伝えすると、不動産を売却する際にかかる税金は4種類ありますが、税金を納めるタイミングは5回あります。
| 税金項目 | 納税タイミング |
|---|---|
| 登録免許税(相続の名義変更) | 名義変更時 |
| 印紙税 | 売買契約締結時 |
| 登録免許税(抵当県抹消) | 不動産の決済・引き渡しの日 |
| 所得税 | 売却した翌年の確定申告の時期(2月16日~3月15日) |
| 住民税 | 売却した翌年の6月に1括、もしくは4分割 |
このように、不動産売却期間内に納めるものもあれば、売却終了後に納税をするものもあります。また、特例などにより支払い時期が変わる税金もあります。
このあとの章で、より詳しいタイミングや、いつどんな税金を納めるのか紹介していきます。事前にしっかり確認し、安心して不動産売却を進めましょう!
不動産売却の税金をそれぞれいつ払うのか把握しよう
まずは、不動産売却にかかる4つの税金「印紙税」「登録免許税」「所得税」「住民税」の納税タイミングをざっくりと把握しましょう。
以下の図をご覧ください。

ご覧のように、印紙税は売買契約締結時、登録免許税は名義変更時と決済・引き渡し日に納めます。
また、所得税は不動産を売却した翌年の確定申告の際(基本的に2月16日から3月15日)に納めます。
住民税も不動産売却をした翌年に確定申告をしますが、6月に一括で納付する方法と、6月・8月・10月・翌々年の1月と四回に分けて納付する方法があります。
不動産売却にかかる税金をいつ払うのかざっくりと理解したところで、ここからそれぞれの税金について詳しく解説していきます。
相続した不動産の登録免許税は「名義変更時」
不動産を相続で取得した場合、不動産の名義変更が必要です。この名義変更に伴って、登録免許税を法務局に支払います。
名義変更の登録免許税の計算方法は以下のとおりです。
- 登録免許税=固定資産価格×0.4%
この固定資産価格は、固定資産納税通知書に記載の金額となります。
印紙税は「売買契約締結時」
印紙税は、売買契約締結時に貼付する収入印紙に対して支払います。
契約金額によって納税額は異なります。以下の表をご覧ください。
| 収入印紙税 | |
|---|---|
| 契約金額 | 本則税率 |
| 50万~100万円以下 | 1,000円 |
| 100万~500万円以下 | 2,000円 |
| 500万~1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万~5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万~1億円以下 | 6万円 |
| 1億~5億円以下 | 10万円 |
登録免許税は「決算・引き渡しの日」
登録免許税は、不動産の決算・引き渡しの日に納税をします。
不動産を売却する場合は、抵当権抹消の登記費用として納めるのが一般的です。
この場合、金額は不動産ひとつあたり1,000円です。土地と建物をひとつずつ売却する場合は、2,000円かかることになります。
なお、抵当権抹消を司法書士に依頼する場合は手数料も含めて1~2万円かかるため、覚えておきましょう。
所得税は「翌年の2月16日~3月15日」
所得税は、暦によって多少変動しますが基本的には売却した翌年の2月16日から3月15日に確定申告をしてから納めます。
また、所得税は不動産売却時に利益が出た場合に課される税金です。また、令和19年までは所得税に復興特別所得税がかかります。売却によって所得を得ず、売却損失をした場合には納税の必要はありません。
また、その税率は売却する不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年を超える場合は15.315%、5年以下の場合は30.63%となります。
※復興特別所得税を含めた税率です。
住民税は「売却した翌年の6月以降」
住民税は、不動産を売却した翌年の6月以降に納めます。
住民税に関しては6月に一括で納付する方法と四回に分けて納付する方法のどちらかを選択できます。四回に分けて納付する場合、納付の期限は6月末・8月末・10月末・翌年1月末になります。
所得税と住民税はどちらも売却翌年に確定申告をする必要があるため、忘れないようにしましょう。
この住民税も、不動産売却時に利益が出た場合に課される税金です。
所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年を超える場合は5%、5年以下の場合は9%となります。
所得税と住民税の税率を纏めると以下の表になります。
| 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税(令和19年まで) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 長期譲渡所得(所有期間が5年超) | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
| 短期譲渡所得(所有期間が5年以内) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
かかる費用・税金は不動産の種類や状況によって異なります。そこで、かかる費用・税金を簡単にチェックしましょう!
必要項目を選択して「かかる費用・税金を見る」を押すと、ご自身の場合にかかる金額や項目の内訳が一覧で表示されます。
 不動産の種類
不動産の種類| 費用・税金名 | 金額 | 内容 |
|---|
| 控除名 | 内容 |
|---|
不動産売却の税金は特例で納税時期を遅らせることもできる
今までは不動産売却における税金の節税方法を解説してきました。
しかし、実際には不動産売却直後は納税が厳しいけれど、後々納税することができる場合もあると思います。
そんな時に、税金を払う時期を遅くすることができる特例があるということも覚えておきましょう。
マイホームの買い換え特例:繰り延べ可能
「特定の居住用財産の買い換え特例」が適用された場合、税金の支払いが繰り延べされます。
この特例は、マイホームを売って新しいマイホームを買い換える場合、一定の条件を満たせば譲渡所得に対する税金(所得税・復興特別所得税・住民税)を繰り延べできるというものです。
売却予定のマイホームの所有期間が10年を超えていることが条件で、適用を受けるには売却の翌年に確定申告をする必要があります。
この特例を利用すると、次に買い換えをする時に繰り延べ分を含めて課税されることになります。なお、繰り延べ可能な金額は、新しいマイホームの購入金額によって変わります。
売却するマイホームより新しいマイホームの方が高額/同額の場合、税金は全額繰り延べになります。新しいマイホームの方が安い場合、その差額に税金がかかります。
この「特定の居住用財産の買い換え特例」は、3,000万円特別控除などの他の控除と併用できない場合があります。
マイホームの買い換え特例について詳しく知りたい方は、国税庁のタックスアンサーNo.3355「特定のマイホームを買い換えたときの特例」もご確認ください。
事業用資産の買い換え特例:繰り延べ可能
マイホーム以外の不動産でも、買い換え特例を受けることが可能です。これを「事業用資産の買い換え特例」と呼び、適用することで税金の支払いが繰り延べされます。
店舗や事業所、農地、貸家、貸地などの事業用財産を売って、新しい事業用資産に買い換えた場合に受けられる特例です。
以下の一定条件を満たす買い換えなら、売却金額の80%を繰り延べることができます。
- 売却・購入ともに事業用の不動産であること
- 売却・購入する不動産が一定の組み合わせであること
- 土地の場合、購入する土地が売却する土地面積の5倍以内であること
- 売却した年、またはその前年/翌年中に購入すること
- 買い換えから一年以内に、その不動産で事業を行うこと
なお、国内であればどの地域との不動産の買い換えにも利用できます。
この場合も適用を受けるには売却の翌年に確定申告をする必要があります。申告時には、特例の適用条件に該当することを証明する書類などを添付します。
事業用資産の買い換え特例について詳しく知りたい方は国税庁のタックスアンサーNo.3405「事業用の資産を買い換えたときの特例」をご確認ください。
不動産売却の税金の納税額を減らすには?
ここまで不動産売却にかかる税金をいつ払うのか紹介してきましたが、「せっかく不動産売却でお金を得たのに税金を取られたら損をした気分だ」「引っ越しを考えていたのに、不動産売却が終了してからも納める税金があるならお金が足りなくなりそうだな…」と考える方も少なくないと思います。
そんな皆さんに朗報です!
不動産売却にかかる税金は、納める額を減らせる可能性があります。
そこで、この章では不動産売却で納める税金の額を減らすにはどうすれば良いのかを詳しく解説します。
購入時・売却時の費用をできるだけ多く計上しよう
所得税と住民税は、他の不動産売却にかかる税金とは違って不動産売却で利益を得た場合に納税義務が課されるものです。
不動産売却で得た利益とは、不動産売却の売却金額から、その不動産を購入した時の費用や、売却した時の費用を差し引いたもののことです。
そしてこの利益のことを、「譲渡所得」といいます。

所得税と住民税は、この「譲渡所得」に先ほど申し上げた所有期間に応じた税率をかけることで納税額が決まります。そのため、人によっては高額になるケースもあります。
所得税と住民税を減らす一番の方法は、譲渡所得を減らすことです。
そのために、不動産の購入費用と売却費用をできるだけ多く計上しましょう。
それぞれ売買契約書や領収書などから確認することができます。
一方、不動産の売却費用はわかるとして、購入時の費用は思い出せないという方もいるのではないでしょうか。
そんなときには、売却価格の5%を「不動産の購入費用」として代用することになります。
しかし、この場合、譲渡所得が本来のものより多くなってしまい、納税額が大きくなりやすいです。
したがって、できるだけ多くの購入費用・売却費用を計上するようにしましょう。
特例を利用して納税額から控除しよう
譲渡所得は特例を利用して控除することが可能な場合があります。
それぞれの不動産事情によって利用可能な特例が異なるので、以下のものを参考にご自身がどの特例を活用できるか確かめましょう。
- マイホームの売却:3,000万円特別控除が使える
- 所有期間10年超えマイホームの売却:軽減税率が適用される
- 相続した空き家の売却:3,000万円特別控除が使える
- 平成21年・22年に取得した土地の売却:1000万円特別控除が使える
控除や特例について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
ふるさと納税で寄付した分も控除される
ふるさと納税で寄付をしていれば、所得税と住民税が控除されます。ふるさと納税で自治体に寄付を行うと、返礼品がもらえることに加え、不動産売却に関する納税額が増えた人はその分だけふるさと納税の控除額も増えることになります。
たくさん税金を納めた人にとって、ふるさと納税は節税対策としても有効です。
ふるさと納税の控除を受けるには、確定申告をする必要があります。
印紙税は売買契約書をコピーすれば節税できる
先ほど、売買契約書に貼付する収入印紙を通じて納める印紙税は契約金額によって納税額が異なるといいました。
この売買契約書は売主と買主の双方の分の契約書を作成する場合は、2通とも課税文書とみなされるため、それぞれに印紙税が課税されます。
しかし、売買契約書を1通のみ作成し、売主と買主で、片方が原本、もう片方が控えとしてコピーを保存する場合には、印紙税の課税対象となるのは原本のみとなるのです。
したがって、買主の契約書のコピーを受け取れば、売主は印紙税を節税することができます。
ただし、後々契約内容をめぐって訴訟となった際、コピーは法的な効力が低いため、注意が必要だということは覚えておきましょう。
他にも詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。



 住宅ローン
住宅ローン 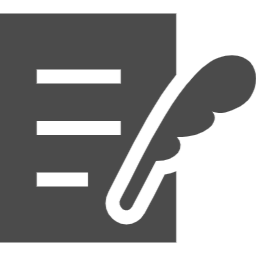 抵当権の抹消
抵当権の抹消  保有期間
保有期間 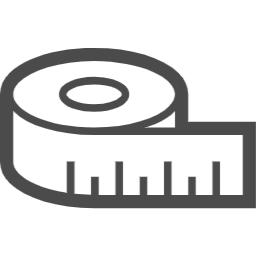 測量を行うか
測量を行うか 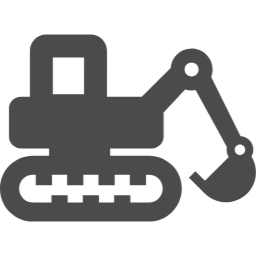 解体してから売るか
解体してから売るか 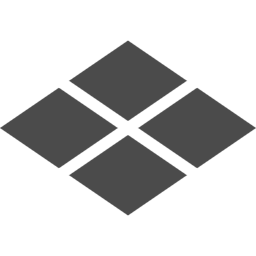 坪数
坪数  ごみ処分するか
ごみ処分するか  ハウスクリーニングするか
ハウスクリーニングするか 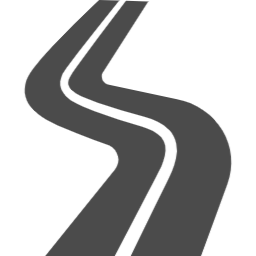 物件の入手経路
物件の入手経路 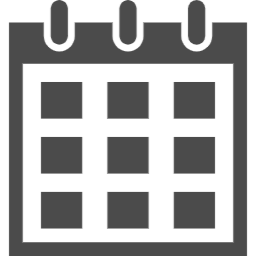 建築年月
建築年月 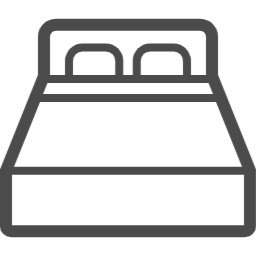 住んでいた時期
住んでいた時期