「まずは不動産売却の基礎知識を知りたい」という方は、こちらの記事をご覧ください。
短期譲渡所得とは
短期譲渡所得とは、土地や戸建て・マンションなどを含む不動産を売却(譲渡)した時に得る売却益のことを言います。譲渡所得には「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」があり、共に異なる税率の所得税や住民税が課せられます。
しかし、不動産の売却価格が「不動産を買った時の値段」よりも低い金額(売却益がマイナス)だった場合の譲渡所得は、課税の対象になりません。
不動産の所有期間が5年以内の場合は「短期」
譲渡所得の中でも、短期譲渡所得扱いになるのは、不動産の所有期間が、5年以内で譲渡が完了した場合になります。この所有期間は、不動産売却において譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以内である場合のことを言います。例えば、2012年5月5日に取得した不動産の売却が、2017年12月31日に完了していたとすると、所有期間は5年以内になるので、短期譲渡所得に分類されます。また、所有期間が5年以上の場合は、長期譲渡所得に分類されます。
短期譲渡所得の計算方法
まずは、譲渡所得についての理解を深めましょう。
譲渡所得はいくらになるのかについてですが、購入した不動産を売却して得た金額全てが、譲渡所得になるわけではありません。不動産の売買では、譲渡にかかるさまざまな費用を、差し引く必要があります。譲渡所得についての計算式は、以下のようになります。
譲渡所得(売却益)=売却金額 -(取得費+ 譲渡費用)
取得費
取得費とは、購入代金や購入時に要した仲介手数料や登記の費用など、不動産の取得に要した費用のことです。不動産購入後に改装している場合には、改装費用の追加も可能です。ただし、経過年数に応じた減価償却費を差し引く必要があります。
また取得費が不明の場合や、実際の取得費が、売却した不動産の5%相当額と少ない場合は、売却価格の5%を概算取得費とすることができます。
譲渡費用
譲渡費用とは、不動産を売却するために直接かかった仲介手数料や印紙税、名義書き換え料などのことです。短期譲渡所得金額が、1000万円だった場合、
①所得税の計算方法:
1000×30.63%≒306万円
②住民税の計算方法:
1000×9%=90万円
③復興特別所得税の計算方法:
306×2.1%=64,260円
- 所有期間が5年以内は「短期譲渡所得」扱い
- 不動産売買でかかった費用を明確にしておく
- 売却益が出るか概算を不動産一括査定に依頼しておく
短期・長期関わらず不動産売却で利益が出た場合、確定申告が必要です。
長期と短期の区分について
- (ア)は、2012年6月1日に不動産を取得して、2017年7月1日に売却しています。
この場合、所有期間は5年1ヶ月ですが、2017年1月1日時点で4年7ヶ月経過ですので、短期譲渡となります。 - (イ)は、2012年6月1日に不動産を取得して、2018年2月1日に売却しています。
この場合、所有期間は5年9ヶ月であり、2018年1月1日時点で5年7ヶ月経過ですので、長期譲渡となります。
保有している不動産を査定してみよう
家の売却を少しでも検討しているのであれば、「自分の家がいくらで売却出来そうか」「利益を出すことができるのか」知りたくないですか?
不動産会社から査定を受けることで特定のエリアの相場価格を知ることができます。特に人気の「イエウール」なら不動産会社に行かずとも自宅で24時間申し込みが可能です。
自分の家に適した不動産会社を紹介してくれるので、膨大な不動産会社の中から選ぶ手間も省くことができます。
まずは、自分の物件種別を選択してから査定依頼をスタートしてみましょう!査定依頼に必要な情報入力はわずか60秒で完了します。
あなたの不動産、
売ったらいくら?
あなたの不動産、
売ったらいくら?
短期譲渡所得に関わる税金や控除について
上記でも記載しましたが、短期譲渡所得に関わる税金や控除について、どのようなものがあるのか、より詳しく見てみましょう。
短期譲渡所得には所得税と住民税が課せられる
短期譲渡所得には、所得税と住民税の他に、2013年から2037年までは「復興特別所得税」を、所得税に合わせて支払う必要があります。復興特別所得税は、基準所得税額の2.1%分です。短期譲渡所得にかかる所得税・住民税・復興特別所得税の税率と計算式は、以下のようになります。| 所得税30.69% | 住民税9% | 復興特別所得税2.1% |
| 税額 =課税短期譲渡所得金額×所得税(住民税)の税率 | 税額 =所得税額×復興特別所得税率 | |
短期譲渡所得の場合、所得税と住民税の税率が、長期譲渡所得よりも高めに設定されています。短期・長期共に復興特別所得税率は同じですが、長期譲渡所得の場合、所得税15%・住民税5%に設定されています。
短期譲渡所得が800万円だった場合の計算方法
仮に、短期譲渡所得が800万円だった場合の計算をして、税額を分かりやすく数字で表していきます。短期譲渡所得が800万円ある時、支払わなければならない税金の総額はいくらになるのでしょうか。以下の表にまとめたので見てみましょう。| 所得税 | 800万円×30.69%=245.5万円 |
| 住民税 | 800万円×9%=72万円 |
| 復興特別所得税 | 245.5万円×2.1%=51,555円 |
| 税金の総額 | 245.5万円+72万円+51,555円=317万500円 |
長期譲渡所得よりも税率の高い短期譲渡所得では、800万円のうち約320万円が税金の支払い対象となります。ちなみに、長期譲渡所得の場合の税金の総額は約169万9,000円で、その差は約150万円になります。
マイホーム売却時の特別控除
不動産の売却で利用できる、控除についても見てみましょう。今住んでいる家などの不動産を売却する場合は、所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。この特例は、「マイホーム特例」とも呼ばれ、別荘のような仮住まい形式の不動産には適用されません。あくまで、居住用の住居に対して適用される特例になります。特別控除適用の場合の譲渡所得の計算式は、以下のようになります。
- 譲渡所得(売却益)=売却金額 -(取得費+ 譲渡費用)-特別控除
マイホーム特例適用要件
マイホームを売った時の特例を受けるためには、下記の適用要件を満たす必要があります。- 売り主本人が居住している家屋や、家屋と共に譲渡する土地であること
- 転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋や家屋と共に譲渡する土地であること
- 災害などにより居住していた家屋が滅失した場合は、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する土地であること
- 転居後、家屋を取り壊した場合は、転居してから3年後の12月31日まで、もしくは、取り壊し後1年以内のどちらか早い日までに譲渡する土地であること(取り壊し後に土地の貸付や、事業の用事で使用していた場合は、適用外になります)

不動産売却にかかる税金・手数料のシミュレーション
不動産売却をした際には譲渡所得にかかる税金の他にも多くの費用がかかります。どのくらいの費用がかかるのかシミュレーションしてみましょう。
必要項目を選択して「かかる費用・税金を見る」を押すと、ご自身の場合にかかる金額や項目の内訳が一覧で表示されます。
 不動産の種類
不動産の種類| 費用・税金名 | 金額 | 内容 |
|---|
| 控除名 | 内容 |
|---|
短期譲渡と長期譲渡はどちらがお得か考えよう
短期譲渡と長期譲渡では、どちらが得なのでしょうか。急いで売却する予定ではない場合、お得になるのはどちらなのか、計算して比較検討しましょう。長期譲渡所得税額は短期の場合のほぼ半分
長期譲渡所得の税率は、所得税15%・住民税5%と、短期譲渡所得と比べほぼ半分になります。そのため、先程の譲渡所得が800万円だった場合を、長期譲渡所得で当てはめると以下のようになります。| 所得税 | 800万円×15%=120万円 |
| 住民税 | 800万円×5%=40万円 |
| 復興特別所得税 | 120万円×2.1%=25,200円 |
| 税金の総額 | 120万円+40万円+25,200円=162万5,200円 |
短期譲渡所得では317万400円であったのに対し、長期譲渡所得では162万5,200円と大きな差があります。なぜ、短期譲渡所得の税率は高いのでしょうか。この税制度の背景には、不動産バブル期の「土地転がし」と呼ばれる転売行為の横行があります。
短期間の転売による利益獲得行為を防止するため、短期譲渡所得の税率は高く設定され、そのまま現在も同じ税率が適用されています。
建物の築年数は短いほど価格が上がる
「短期譲渡所得よりも、税率の低い長期譲渡所得のほうがお得なのではないか」と思う人もいるでしょう。しかし土地と違い、経年劣化する建物では、築年数が短いほど売却時の価格は高くなります。基本的に、建物の築年数は1日でも早いほうが高く売ることができるので、5年以内の物件と10年ほど経過した物件では、価格に大きな差が生じます。短期譲渡所得の税率で、売却の時期を迷っている人は、インターネットで手軽にできる一括査定を利用しましょう。5年以内の売却が適しているのか、いないのか、築年数を変えて査定することができます。ネットの一括査定なら、最大6社の査定が可能なイエウールがおすすめです。
固定資産税は短期間なほど負担が軽い
不動産という資産があると、必ず支払わなければならないのが固定資産税。長期譲渡では、譲渡所得税を節約できたとしても、固定資産税は支払わなければならないので、結果として高くつくことがあります。仮に、固定資産税評価額が1,000万円の場合、毎年支払う固定資産税は14万円。他に、都市計画税や維持費や管理費など、長く所有することでかかるお金は大きくなっていきます。とくに、既に居住していない不動産の場合は、短期譲渡で売却したほうが無駄なコストを削減できるため、結果的にお得になります。
- 税率は短期譲渡所得が高い
- 築年数は浅いほど高値に
- 不動産の維持費も考慮
年問題を見越した譲渡計画を
「生産緑地」という看板を目にしたことはありませんか。2022年問題とも言われている「生産緑地」という看板は、1992年に生産緑地法改正で、都市部の一部の農地を「生産緑地」に指定し、固定資産税や相続税についての優遇措置を与える代わりに、30年間の営農義務があります。この営農義務のある「生産緑地」の期限である2022年が近づくことで、問題視されているのが不動産の暴落。「生産緑地」は期限が切れた後、自治体は行政に買い取り請求を行うことができますが、大量にある「生産緑地」を買い取ることは、財力的に難しいという見解が示されています。多くの自治体が「生産緑地」を売却すると予想されており、需要と供給のバランスが崩れて、不動産の暴落が起こると考えられています。したがって、不動産譲渡を検討しているのなら、2022年問題を見越した計画を立てましょう。



 住宅ローン
住宅ローン 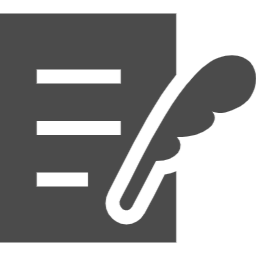 抵当権の抹消
抵当権の抹消  保有期間
保有期間 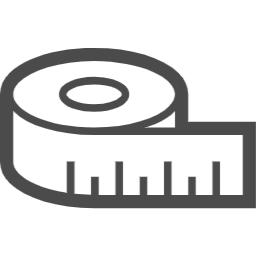 測量を行うか
測量を行うか 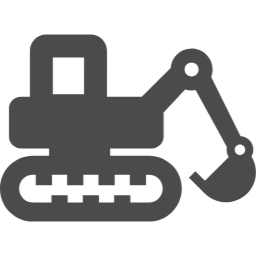 解体してから売るか
解体してから売るか 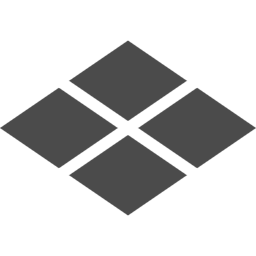 坪数
坪数  ごみ処分するか
ごみ処分するか  ハウスクリーニングするか
ハウスクリーニングするか 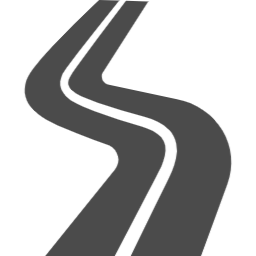 物件の入手経路
物件の入手経路 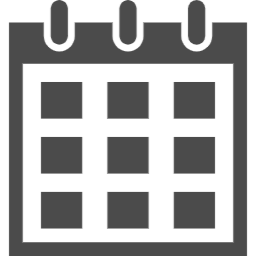 建築年月
建築年月 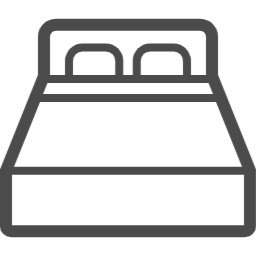 住んでいた時期
住んでいた時期